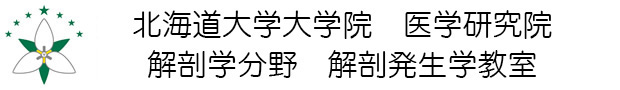2008年度(平成21年3月発行 フラテ95)
今年が、私が解剖発生学分野の担当教授となって10周年にあたることから、現在に至るまでの研究の経緯を「自分史」としてまとめ、これから自分の道を探し始める医学部・医学研究科の学生さんに読んでもらうこともよいかと思い、このような筆を執ることにした。
1. 学生時代(1978-1984年):解剖学に進むきっかけ
東北大学医学部3年の解剖学実習の時、当時32才で西ドイツ留学から帰ったばかりの内山安男助手(現在、順天堂大学医学部教授)に声をかけられ、解剖学教室に机をもらい、ここから講義や実習に向かう生活が始まった。ほどなく、内山先生が筑波大学の助教授として転任したため、夏休みなどを利用して常磐線経由で筑波学園都市へ向かい、筑波大学医科学修士棟電顕室のソファーに寝泊まりしながら、電子顕微鏡を使う研究を開始した。5年生の時には、1年間の130日を筑波大学で過ごした。卒業後の進路を解剖学に決めた理由には、内山先生との出会いに加え、当時新潟大学医学部の藤田恒夫教授の存在もあった。その頃藤田教授は、走査型電子顕微鏡や免疫組織化学の形態学的データに基づき内分泌細胞からニューロンまでを包括するパラニューロンという新たな概念を世界に向けて提唱しており、その解剖学に憧れと魅力を感じたのであった。
病院実習の最初が脳神経外科であった。「もやもや病」の命名者でもある鈴木二郎教授は、医局員にとっては鬼軍曹のような怖い存在で、その脳外科は大学病院の診療科でありながら主要な診療の場所を学外の広南病院に持つ、軍閥のボスのような教授であった。それでいて、ポリクリで回ってくる学生と話をするのが好きな教授で、ある日、「君は解剖に行くと聞いたが、どこの誰の所にいくかね?」と聞かれた。筑波大学の内山先生か新潟大学の藤田教授の所と答えると、「どっちが若い?どっちが有名?」と聞かれた。それに答えると、間髪を置かずに「君は筑波に行きなさい。名を成した人よりは、これから名を成すかもしれない人にかけた方がいい」。これで筑波大学の大学院進学に決めた。あの時の鈴木教授の指南は1つの真実であると、今でも思っている。
2. 大学院・助手時代(1984-1992年):解析技術の習得と薄まる方向性
4年間の大学院では膵臓ランゲルハンス島の日内変動をテーマとして解剖学的研究を行い、次の4年間は金沢大学医学部そして東北大学医学部の解剖学助手として近藤尚武教授の下で末梢神経系の組織化学的研究を行った。この8年間は、与えられた研究テーマの遂行の中から将来に続く自己の研究テーマの糸口を見つけ出そうと必死に模索した。しかしそのような出会いが未だないことを自覚し、その分だけ解析技術の習得にかける8年間となった。ちょうどこの時期は分子生物学が隆盛しその頂点に向かっていた。このため習得した解析技法も、遺伝子クローニング→ノザンブロット・PCR→in situハイブリダイゼーション法などの遺伝子発現解析法と、タンパクの単離精製→抗体作成→金コロイド免疫電顕法などのタンパク局在解析法になった。この時代の流れに巻き込まれながら分子生物学への憧れも強まり、心は解剖学から離れつつあったことも事実である。
最初のボスの内山先生から学んだ最も大事なことは、思い立ったらまずやってみるという「頭よりまず体を動かせ」の武闘派的スピリットである。次のボスの近藤先生から学んだことは、「やったことはきちんと論文にまとめる」の習慣だと思っている。
3. 北大助教授・教授時代(1992年-現在):神経解剖学研究を目指して
1992年、北大医学部解剖学第一講座の助教授として赴任することとなった。32才の時である。北大赴任と同時にたった一人で開始した研究が、当時クローニングされたばかりのグルタミン酸受容体の遺伝子発現解析である。その流れで、やがて遺伝子ノックアウトマウスの形態学的解析にも巻き込まれるようになった。遺伝子発現解析の開始により、次にタンパク分子レベルの解析で勝負の分かれ目となる高品質抗体作成とそのシナプス局在解析能力が重要になることを自覚した。遺伝子ノックアウトマウスの形態学的解析への参入は、顕微鏡やマーカー・トレーサー分子を駆使する高い神経回路解析技法が必要になることを悟った。さらに、激しいグルタミン酸研究競争に参加することにより、日夜を惜しまず研究に励む分子生物学者や電気生理学者の存在を知った。ここに至って、自分が行うべきことは分子生物学の後追いでもなく、電気生理学への無いものねだり的なあこがれでもなく、足元の神経解剖学であることを認識した。大学院進学から8年もたって、ようやく腹が決まったのである。それからは、予想を超える形で、すべてが順風満帆で今日まで来ている。その最大要因は、人に恵まれたことである。しかもタイムリーに。
主任の井上芳郎教授とは1992年の赴任時が2回目の顔合わせで、実はほとんど何も知らずに北海道に来た。最初に言われたことは「研究に口は出さないから、自分で思うようにやりなさい」であった。つまり、3人目のボスは、共同研究も研究費も対外的事項も各人の自由(自己責任)をポリシーとする、北の大地を絵にしたような人物であった。束縛もなければ指導助言もないような環境に突如置かれた当初は、一体何をどうしたらよいのか迷うことの方が多かった。しかし、異分野の研究者と頻繁に連絡を取り合い常に自己判断が必要とされる状況になると、この環境は魚に水を与えるように機能した。
解剖学第一講座の助教授時代(1992-1998年)には、それぞれが強い目的や個性を持つ臨床系の大学院生を中心とした研究チームが、自然発生的にできた。中川伸(医学研究科、精神医学)、栗原秀雄(医学研究科、耳鼻咽喉科)、柴田隆(医学研究科、泌尿器科)、土岐(和田)志麻(歯学研究科、小児歯科)、田中淳(獣医学研究科、獣医解剖)、山田恵子(医学研究科、神経内科のち第一解剖)の大学院生の面々である。どっぷりと解剖学教室に軸足を置き、実質的に神経解剖学研究の立ち上げをやってくれた。また、第一解剖助手の市川量一(現在札幌医科大学医学部講師)も、登上線維の連続電顕解析でシナプス回路発達研究に加わるようになった。2002年の河合塾が別冊宝島として出版した「わかる!学問の最先端:大学ランキング理科系編」の神経形態学部門で、当該分野が第3位にノミネートされた。そのコメント('臨床畑の若い研究者が集まり活気にあふれているのが特色。分子生物学に通じた、時代の先端を行く新しい神経形態学を拓かんとして注目される')を読むと、まさにこの研究チームを指しており、どこかで誰かが見ていたことに驚いた。
解剖学第一講座の助教授から第二講座の教授への移行期には、山田和之(医学研究科、耳鼻咽喉科)、大島昇平(歯学研究科、小児歯科)、山下登(医学研究科、泌尿器科)、深谷昌弘(医学研究科、解剖発生)、山崎美和子(医学部学生)、高崎千尋(歯学研究科、小児歯科)、佐藤和則(医学部学生)、中村美智子(医学部学生)、宮崎太輔(医学研究科、解剖発生)、境和久(理学研究科)岡田(横山)理恵子(歯学研究科、小児歯科)と、実に多彩な大学院生と医学部学生が集まってくれた。ここから、現在の助教3名(深谷、宮崎、山崎)が誕生している。
その後、分野の教育研究体制も次第に整う中で、立川正憲(東北大学薬学研究科、研究指導委託)、三浦会里子(医学研究科、解剖発生)、大森優子(医学部学生)、藤原百合(歯学研究科、小児歯科)、野村幸(医科学修士、解剖発生)、吉田隆行(医学研究科助手)、江本美穂(医学研究科、解剖発生)、湯浅寛加(医科学修士、解剖発生)、内ヶ島基政(医学部学生、のち医学研究科解剖発生)、岩倉淳(医科学修士、解剖発生)など、解剖発生学分野所属の大学院生が中心となってきている。
この間ずっと、私よりも第二解剖歴が長い石村知子が元気にテキパキと教育研究の補助業務と事務をこなし、技術職員の清水秀美が解剖学実習の運営に重要な任務を果たしている。教室立ち上げ間もない頃には、小林(内沢)友子も事務を担当してくれた。
文責:渡辺